らした先生の「writingの現場」を見た感想。ブログ執筆ツールとしてのアウトライナーとエディタに思うこと。
この記事を読むのに必要な時間は約 15 分 57 秒です。

どうも、最近WRMを購読し始めた怜香@Ray_mnzkです。
WRMというのは、「らした先生」の愛称でも親しまれている倉下忠憲さんが発行なさっているメルマガ「Weekly R-style Magazine」の通称。この度250号を迎えられたとのこと……おめでとうございます!
メルマガ | R-style |
私はまだ購読し始めたばかりで、実を言うと購読始めて最初に届いたのがこの記念すべき250号だったのですが……そこにとても興味深いコンテンツがありまして。色々と気づきがあったので、記事としてまとめてみようと思います。多分、オチは……ないです(笑)
らした先生の「writingの現場」動画
そのコンテンツとは、「writingの現場」という動画です。「らした先生」こと倉下忠憲さんが、ご自身のブログ執筆の様子を動画に収めたものです。
「writingの現場」を公開します。 | R-style |
この「writingの現場」、もともとはメルマガ「Weekly R-style Magazine」250号に掲載されていたものなのですが、ブログ「R-Style」の記事として公開もされています。
これから語る「writingの現場」動画一覧は上の記事の中にあります。まずは是非そちらをご覧くださいませ。
「writingの現場」を見て気づいたこと
さて、「writingの現場」を一通り見てみたところ、気になった点が色々とありました。後ほど詳しく見ていきますが、ひとまず先に列挙しておきます。
- 見出しは後から入れる
- 下書きの文章を見ながら、そのすぐ近くに清書を書く
- 下書きの文章にそのまま肉付けする
- エディタ上で、下書きの構成を組み替える
- 改行の多用
- 読み返しに時間をかける
- あえて一続きの長い段落で書いておいて、後から区切る
- 「書いては消し、書いては消し」の校正作業
私が動画を見ていて気になった点は以上です。自分の執筆スタイルと似ていて「それ私もやってる!」と思えた部分もあれば、「その発想はなかった!」と思えたものもいくつかありました。とにかく、気づきの連続です。
この記事を書き出す前に、動画を何度も止めながらWorkflowyにメモしていく形で感想(というか段差)を書きました。 → らした先生の執筆現場 – WorkFlowy
今回の記事は、この感想アウトラインにがっつり加筆(ついでに少し修正も)してできたアウトラインをするぷろXに移して書いています。
……前置きが随分長くなりました。そろそろ本題に入っていきましょう。
見出しは後から入れる
まずは一番衝撃を受けたことから。気付いた点は、以下の通りです。
- 「ここで話が変わる」という位置に、見出しタグだけを入れておく
- あとから見出し文を書く
- 区切りが必要ないと思ったら、さくっと消してしまう
これを見た時、「見出しとは、長くなった本文を適切に区切るためのもの」という発想のように思えました。文章という「中身」の塊に「仕切り」を立てて小分けにしていくようなイメージです。
実を言うと、私にはこの発想はありませんでした。私の場合、エディタであらかじめ文章を書いておいて「あとから区切る」ということはまず無いのです。
というのも、私はWorkflowyで下書きする段階で、先に構成も見出しの枠組みも決めてしまうんですよね。先に「箱」をいくつも用意して、あとでその中に「中身」を入れていく感じです。
そして、「あとから見出し文を書く」ということ。
これも私はやっていないです。Workflowy上で仮の見出し文だけつけておいて、するぷろXに移して本文書いてから適切な見出し文に書き換えることはありますけどね。「本文書き上げてみたら、最初想定していたお題とは少し変わっていた」ということはよくあります。
ですが、
- 見出しを「仕切り」と捉えるなら、仕切る段階では名前はなくても問題ない
- 見出しを「箱」と捉えるなら、名前を決めておかないと中身を入れていけない
こう考えると、あとから見出しを入れた場合、名前は後付けで構わないというのは納得できました。
また、「区切りが必要ないと思ったら、さくっと消してしまう」という点。エディタ上で見出しを入れたり消したり……エディタ上ではあるけれど、なんとなくアウトライナーっぽい作業をしているように思えてきます。
下書きの文章を見ながら、そのすぐ近くに清書を書く
続いてはこちら。これは、私も時々やっているなぁという印象です。
- 大幅に加筆されている
- その部分の清書が終わったら、その部分の下書きは消す
- 加筆の結果(下書き段階の)前後の文と文脈が繋がらなくなったら、前後文の方を修正する
これらはどれも「わかるわかる!」と大いに頷けました。なるほど、だから本番の方が下書き(アウトライナー)段階よりも文章量が増えるんですね。そういうものなのだと分かって安心しました(笑)
この「下書きから清書となる文章を作る」っていう作業、少しずつ文章を「可変から不変に変えていく」感じがしたのです。
下書き状態の文章は、まだこれから加筆されたり修正されたりして「変わる」予定のあるもの。それに手を加えていって、最終的に「これ以上書き直さない」完成形にしていく。文章を「固める」作業のように思えてきます。
下書きの文章にそのまま肉付けする
私がよくやってるのはこれですね。下書きの使い回し。
- 下書き文をそのまま使いまわせる場合はこの方法?
- 肉付けしてた途中から切り離して清書することも
後者の作業は私はそんなにやらないのだけれど、言われてみれば確かに、肉付けだけで完成形の文章を作ろうとしても上手く仕上がらないことがありますね。
そういう時私は割と無理やり完成形にこじつけようとするのですけど、そうではなくその部分を改めて書き直したほうがいいこともありそうです。
エディタ上で、下書きの構成を組み替える
これがある意味一番興味深かったことですね。
- その時々で、エディタ上でコピペして下書き文を移動させている
- エディタ上で直接アウトラインを組み替えている
- 構成変更も「その場で対応」
- かなり大幅な構成変更もやっている(かなり遠い位置の下書きを移動してきていたりする)
こういう作業って案外やる人多いんじゃないかと思うのですが……これって、要するに「アウトライナーでやるような作業をエディタ上で行っている」んですよね。
らした先生の場合は初めから全てエディタ上で執筆してらっしゃるから必然的にそうなるのかもしれませんが、最初の構成はアウトライナーで練るという人でも、エディタに移した後に構成を組み替えることってあると思うのです。私はよくあります。
エディタに移した後に構成変えたくなったら一旦アウトライナーに戻す場合もあるかと思いますが、コピペでも対応できるような一つ二つ程度の入れ替え作業なら、エディタ上でも出来ますし、エディタ上だけで完結するので作業も早いです。
ちなみに私の場合は、見出しとそこに続く本文を丸々別の位置に移動させたり、エディタで書いていくうちに蛇足に思えてきた見出しはその下の本文ごと削除したりもしています。アウトライナーで作った下書きとエディタで完成させた記事は大幅に違っていることも少なくないんですよ(笑)
いずれにせよ、本来アウトライナー上で行うような作業もエディタ上で行っているということです。
こうして見ると、アウトライナーとエディタの役割分担ってかなり曖昧なものなのかなと思えてきます。実際、これとは逆にアウトライナー上で清書まで全て行う人もいるわけですし。大変興味深いです。
改行の多用
これはやる人も多そうに思ったのですが、ひとつ気になった点がありました。
- 段落ごとに空行を挟んでいる
これはやはり、読みやすくするためでしょうか。確かに、適度に空行が挟まっていた方が読みやすいです。
ただ、これ、するぷろXで書く場合は不要そうです。するぷろXでは投稿時に自動的に段落がpタグで囲まれて、記事として公開された際には自動的に行間が生まれるからです。
するぷろXに限らず、Wordpress側で自動整形をオンにしている場合は、意識的に空行を挟まなくても読みやすい形になるものと思われます。
読み返しに時間をかける
これは誰しもすることでしょう。ただ、単純に頭から読み返しているだけというようには見受けられなかったので、少し考えてみました。
- 同じ部分を何度も読み返している?
- 文章がしっくりくるまで(読んでみて違和感なくなるまで)読み返し・修正を行っている?
そう、気になったのは、「同じ部分を何度も読み返しているように見えた」ことです。書いている分ごとに、清書してすぐにじっくりと読み返して、気になったところは納得いくまで手直ししているように思えたのです。
確かに、記事の部分ごとに分けてじっくり読み返すことで、日本語上の違和感には気づきやすくなるように思えます。頭から読み返すと、話の繋がりの違和感は気づきやすいけれど、誤字脱字とかは案外見落としがちなので。
あえて一続きの長い段落で書いておいて、後から区切る
これは一番初めに挙げた「見出しは後から入れる」に通じるものがありそうです。
- 書いたその場で区切りを決めてしまうわけではない
とりあえず書けるだけ書いておいて、あとから改行したり文章を分けたりする。やはり、「後から見出しを入れる」作業に似ているように思います。
確かに一段落が長かったら読みづらいですから、改行して程よい長さに調節した方が望ましいですね。どんなに記事内容が素晴らしくても、読みづらかったら誰も最後まで読んでくれませんから……。
「書いては消し、書いては消し」の校正作業
そしてもうこれはすごく共感できます。
- 下書き→清書、かと思いきや清書に清書を重ねている
- カーソルで追いながら読んでいる
- 「こうかな……違う、じゃあこうかな……違う」の繰り返しが見える
下書きができたらすぐ清書……かと思いきや、案外そうではないんですよね。清書のつもりで書き直しをしても、もう一度読み返したらまた直すべきところが見つかって書き直したり……なんて、それこそ日常茶飯事と言ってもいいぐらいです。
こうなってくると、いったいどこまでが「下書き」なのだろう、と思えてきます。下書きと清書を分けて捉えようとしていること自体間違っているのかもしれません。
そしてこの「書いては消し、書いては消し」の校正作業は、本当に共感できる作業なんですよね。ちょっと書き出してもうまく言葉が続かなかったら消して……という作業を、納得いく文章になるまで何度も繰り返します。
実際のところ、これをきちんと手を抜かずに行うことが、読みやすく分かりやすい記事にするために一番大切なことなんじゃないかなと感じます。もっとも、たまに面倒になって放り投げてしまうこともありますけどね(笑)
「writingの現場」を見て、これから考えていきたいと思ったテーマ
「writingの現場」動画を見て気づいたことは以上です。本当にたくさんの気づきがあって、それを列挙していくうちにさらに発見があったりして、これから考えていきたいなと思えるテーマがいくつも浮かび上がってきました。
先にある程度の文章を作ってから「区切り」を入れる形で見出しを入れていく
これは私の記事執筆スタイルとは違う執筆の仕方。私にはなかった発想だからこそ、気になるというものです。
はじめから見出しの枠組みを決めておくのではなく、あとから文章を区切っていく。枠組みは、あとから生まれてくる。
私はアウトライナーで構成組む段階でもまず先に見出しを意識してアウトラインを作っていくので、こういう方法で書くとまた違ったテイストの記事が書けるのかな?と想像していたりします。いつかこのやり方でも書いてみたいです(普段やらない書き方なのですぐには出来なさそう……)。
アウトライナーで行うような作業を、エディタ上で行っている
そしてこれ。今回「writingの現場」を見てもっとも考えたくなったのが、「アウトライナーとエディタについて」でした。
この「writingの現場」で、らした先生は、
- 下書きとなる文章を書く
- 並び替えるなどして構成を決める
- 肉付けや修正を行い、清書となる文章を仕上げていく
という執筆作業を、すべてエディタ上で行っておられます。
このうち、(2)の作業は、アウトライナーで行われるような類の作業です。それをエディタ上で行っているわけですが、やっていることは同じです。下書きを一旦アウトラインとして捉えて構成を練っているわけですから。
そう考えると、アウトライナーでやれることはエディタ上でもできるはずということになってきます。
エディタでも行えることを、わざわざアウトライナーでやる意味とは?
そんなわけで、単純に項目を組み替えて構成を練るだけなら、わざわざアウトライナーに頼らなくても、エディタ上で十分できるのです。
それでは、わざわざアウトライナーで構成を練るメリットは何なのでしょうか。
考えられる理由としては、
- 構造が見やすくなる
- 組み替えがしやすい
- 階層化することで浮かび上がってくるものがある?
といったところでしょうか。
特に階層化は、エディタでは出来ない作業です。そこに、わざわざアウトライナーを使って記事構成を考える理由があるのではないかと感じます。
ただ並べるだけではなく、段差を作って並べることで、思考が深まっていく。それを行うことで初めて生まれてくるものがあるのではないか……そんな風にも思えます。
アウトライナーとエディタの境界
こうなってくると、「どこまでがアウトライナーの仕事で、どこからがエディタの仕事か?」というのが気になってきます。
やろうと思えば、アウトライナーできちんと文章化して完成稿を作るところまで行うこともできます。その一方で、構成の組み換えまで含めて、全てをエディタだけで完結させることもできるのです。
どこまでをアウトライナーでやって、どこからをエディタに託すか。それはやはり、人によって様々なのかもしれません。アウトライナーとエディタの役割をそれぞれどう考えているかによる部分もありそうです。
もしかしたら、アウトライナーとエディタの境界は、ツールにはよらないのかもしれません。ツールではなく、「やること」で決まるような気もしています。
今日のあとがき
こんな感じで、「writingの現場」から、いろいろなテーマが浮かんできました。これらに関して、今の段階では、まだこれ以上思考は深まっていません。だから、今はまだ何ともオチはつけられていません。
今回浮かび上がってきたテーマをどれだけ掘り下げられるかはまだわかりませんが、これから少しずつでも考えていきたいです。……うまくまとまるかどうか不安しかありませんけど!(笑)
それにしても、自分がやっていることを他の人はどうやっているのかを見るのって、本当に勉強になりますね。自分ひとりでやっているだけでは気付けなかったことに気づける。そしてそれをヒントに、より深く考えたり、やり方を改善したりできる。
私も今回の経験を活かしていけたらなと思います。らした先生、とても勉強になるコンテンツをありがとうございました!
それでは、今回はこのあたりで。
関連記事
-
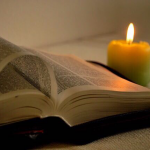
-
解き明かされ繋がっていく物語。2017年〈びっくら本〉紹介 #mybooks2017
2017年に読んだ面白い本を紹介するという、倉下先生の企画〈びっくら本〉。ちょうど今年のめり込んだ小説があったので、〈びっくら本〉として紹介することにする。
-

-
それは「誰」の物語なのか。 〜らした先生からの「成功者の本」にまつわる3つの設問を考えてみた
8月20日に倉下忠憲さんがブログ「R-Style」に投稿なさった、「成功者の本」という記事。この記事には、「成功者の本」にまつわる3つの設問がある。今回は、この3つの設問について私なりの解答を示してみることにする。



